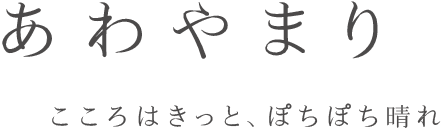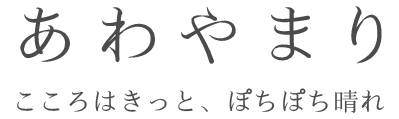2019/12/24
今はまだ、おひとり女子
カピバラは片想いをしていた
少し年上の先輩は
職場が同じだし
今はただ見ているだけで幸せだった
少し前に人気を博したカピパラも
最近はさほどでもない
まだ学生だった頃は
カピバラだというだけでモテた
彼氏もいたけれど
元々おとなし性格で
一人でいるのが好きなので
あまり長くは続かなかった
それに
スキンシップをとるようになると
どの彼氏も言うのが
きみ、見かけより毛が固いんだね
と言うことで
それがカピバラのコンプレックスになった
確かにカピバラの毛は
うさぎのそれよりも固いらしかった
でもそんなこと
カピバラのせいではない
撫でていて気持ちよくない
と言うのが最もだとしても
そんなわけで
カピバラは片想い中の先輩に
毛を触られないように気をつけた
片想いの間だけでも
夢をみていたいのだ
先輩は時々
後輩の女の子(自分と同期だ)の頭を
ポンポンとすることがある
あれをやって欲しい気は満々だが
やはり毛が心配だった
年末の忘年会で
先輩と同じテーブルになった
いつも口数のすくないカピバラだが
恥ずかしくてもっとしゃべらなくなる
あの同期の女の子も同じテーブルだった
話はクリスマスも目前
みんなの予定は?という話だった
先輩は
僕は気になる子と
イルミネーション見に行くんだ
と言った
そのとき同期の女の子が
恥ずかしそうに笑ったのには気がつかず
盛り上げ役の男の子が
えー、まじっすか
誰と行くんですか〜
どんな子タイプなんですか?
と聞くと先輩は
えっと、誘うのはまだなんだけど
ほぼほぼね
やわらかい感じの子だよ
そう言われて
カピバラは敏感に反応した
やわらかい感じ
私だって心はやわらかだわ
自分に質問が回って来た時
動揺もしていたからか
ええ、今年も彼と温泉に
なんて言ってしまったカピバラ
社内のうわさ話で
先輩と同期の女の子が付き合っていると
耳にするのは間もなくだった
クリスマス
カピバラは月一のご褒美として行く
温泉施設に来ていた
ここで一ヶ月の疲れと
失恋の痛みを洗い流すのだ
温泉につかり
美味しいものを食べ
温泉につかり
甘いものを食べ
夜景をみる
施設の浴衣をまとい
夜景を見ながら
来年は有言実行
好きな人と一緒にイルミネーションを見るぞと
心に決めたカピバラだった
(c) 2016 あわやまり
2019/12/22
やさしくてあたたか
子どもが
大きくなることの
なんて早いことだろう
こないだ
小学生だった親戚の子が
もう大学四年生
すっかり大人の女性になっていた
大きくなったね!
つい、言ってしまう
わたしもかつて
よく言われたなあと思い出す
大きくなったね
もうそんなになったの!
驚きに満ちた声で
その度
どうして大人は
おんなじことばっかり言うんだろう
と思っていた
でも間違いなく言えることは
大きくなったね
と言う言葉には
よくがんばって大きくなったね
元気でいてくれて嬉しいよ
なんてことが
きっと
込められていると言うこと
だからどうか
子どものみなさん
もう十分大きくても
誰かの子どもであるみなさん
大きくなったね
もうそんなになったの!
と言われても
またか
と思わずに
はい、こんなに大きくなりました
なんて誇らしく
思ってくださいね
そうして元気に生きていてくれること
それが喜びでもあり
願いでもあります
(c) 2018 あわやまり
2019/12/20
元気のないとき
ひとりぼっちで部屋にいて
小さな声で
言ってみる
おーい、だれかぁ
おーい、だれかぁ
それは母親か
恋人か
それとも
私の赤ん坊か
分からないけれど
私はだれかに
抱きしめて欲しいらしかった
赤ん坊なら
私が抱きしめることになるけれど
無条件の愛のような
そんなぬくもりを
欲していたのだと思う
それはもう簡単には
得られないのを分かっていて
(c) 2017 あわやまり
2017年春号「夢ぽけっと」より
2019/12/17
お話のような
駅の改札を出たら
声をかけられた
振り返っても誰もいない
こっちです
と下から声がする
足元になんだか風を感じて
下を見るとヒラメがいた
あなたを今年の
「涙プリンセス」に決定しました
つきましては広報誌に載せたいので
インタビューをよろしいですか?
わたしはびっくりして
でもまずしゃがんで
えっと、すみません
なんですか?「涙プリンセス」って?
するとヒラメは
まばたきを一つして
ええ、わたくしどもは
この駅のホームで
お客様がこぼされるため息や
おとされる涙を
人知れず食べているのです
年々わたくしどもが増やされているのには
ため息や涙が増えてきているから
なんですね
あ、ちなみにわたくしは
下りのホームをまとめています
ヒラメ係長です
とヒラメは言う
それで?
とわたしが解せない顔をしていると
あ、失礼しました
それで今年から
何か楽しいことに役立てたいと
この沿線の会社からのお達しで
この一年で一番たくさん
ため息をこぼした「ため息キング」
涙をおとした「涙プリンセス」
を探して表彰し
広報誌にもコメントをいただこうかと
わたしはあきれて
そんなのいやです
それ嬉しくないですよ
表彰されても
失礼します
わたしが立ち去ろうとすると
ああ、すみません
ちょっとお待ちを
ヒラメは水もないのに
す〜と近づいてくる
写真やお名前などは載せません
一言だけでも
もう決まったことゆえ
上がうるさくて
「ため息キング」はくださいましたよ
わたしは立ち止まって聞く
ため息さんはなんて?
「ため息をつくのは、駅だけと決めています。
キングになれて複雑な気分です。
来年はもっと明るい賞を作った方がいいですよ。」
ほら、やっぱり
変ですよこんなの
とわたしが言うと
でもわたくしが決めたことではなく
わたくしも日ごろは
ため息と涙を食べている
しがないヒラメなんです
と言い返され
ヒラメの上下関係なんかを思ったら
少しかわいそうになり
ふーっと息を吐いてから一気にしゃべった
「プリンセスになったのは初めてですが、
駅で泣くとすっきりして家に帰れます。」
これでいい?
ヒラメ係長は
ありがとうございました
あの〜、それで
お名前などはもちろん載せませんが
何かニックネームのようなものを
お願いしたいのですが
勢いがついたわたしは少し考えて
「なにもかもが蜃気楼」
と答える
結構でございます
お時間をとらせてすみませんでした
広報誌と賞状は改めてお渡しします
では
と言ってヒラメ係長は
す〜と急ぎ気味に
わたしから離れて行った
バスロータリーに向かいながら
はじめての 涙プリンセス 蜃気楼に泣く
とつぶやいた
(c) 2010 あわやまり
私家版詩集「今日、隣にいたひと」より
詩集「記憶クッキー」はこちらから→
2019/12/15
いろいろ考える
人はしばしば
あのひとは幸せだったのだろうか
なんて
もう本人に聞けないことを
考えたりする
もしその答えが
天国から送られてくる
なんて仕組みになっていたら
どうだろう
しかもそれが
幸せでなかった
だとしたら
私たちは更なる後悔を
背負うことになるだけだ
だから
残されたものたちは
想像するくらいしか出来ないことが
この世の
うまくできた仕組みなんだと思う
(c) 2019 あわやまり
2019/12/11
いろいろ考える
作りもの
の中に
本物のようなもの
を感じ
現実
の中のそれは
当たり前ではあるけれど
思い描いていたものとは
かけ離れていて
それは当然
本物なのだけど
作りもの
あるいは
夢の中のもの
が本物みたいに
に思えるのは
何故だろう
(c) 2019 あわやまり
2019/12/10
伝えたいこと
学校の先生や家族の前では笑わなきゃ
喉の奥がつまるようなこの苦しさは
知られちゃいけないって
がんばっているあなたへ
まず 今あなたがいる
そのスープの中から出ておいで
それから
だいぶ疲れてしまっただろうから
安心できる温かいお茶の中で
ゆっくり休もう
それで 元気になったら
他のお皿をのぞいたり
違うテーブルに行ってみたりしよう
そこにも世界はあるから
今いるスープの中だけが
世界の全部じゃない
あなたが生きるべき場所の
全てじゃない
居心地のいいテーブルを見つけたり
あなたの良さを活かして
美味しいスープをつくることもできる
まずいスープしか知らないで
終わりにしてしまうのは
もったいない
テーブルは いくつもある
スープも たくさんある
あなたに合ったスープが
広い世界に 絶対ある
(c) 2007 あわやまり
「一編の詩があなたを強く抱きしめる時がある」(PHP研究所)
「ぼくはぼっちです」(たんぽぽ出版、現在あわやまりオンラインショップで販売↓)
「子どもと一緒に命をみつめる詩」(たんぽぽ出版)より
2019/12/08
いろいろ考える
インドのカルカッタの駅で
目だけは深く澄んで
きらきらしている少年が
明日を探している
通り過ぎる
忙しそうに働く人々がくれるのか
旅行に来た
外国の人たちがくれるのか
信じているのか分からない
神か仏がくれるのか
少年の明日は
どこに行ったらあるのか
こんなに貧しさと豊かさの差があって
こんなに自分は何も持ってなくて
こんなにたくさんの人がいる国で
1年に8万人の子供が行方不明になる国で
どうして、と
問うことも出来ないまま
ひたすらに明日を探している
(c) 2018 あわやまり
2018年「秋美vol.30」より
2019/12/07
いろいろ考える
前に知り合いの人が
「環境がつくりだした友達」
という言葉を使った
学校や会社
アルバイトに習い事
その場にいるから友達だけれど
その場がなくなると
会わなくなるような人のことだ
大人になれば
そういう人が今までに
たくさんいたなぁと思い返す
その人たちも
人生の限られた間だったけれど
その時はとても大切だったよ
ありがとう、元気でいてねって
心の中で、思っている
そして
今も仲良くしている友達は
大切な宝のような
ほんとうの友達だから
これからもどうぞよろしく
いつもありがとう、って
直接会って、言いたい
(c) 2018 あわやまり
2019/12/04
お話のような
のびはうらやましかった
ぼくは人が伸びをしたときに
出てくる
それは寝起きの
まだ眠たい伸び
ずっとパソコンで仕事
肩が凝ったときの伸び
ぼくが双子なら
だいぶ違ったのに
のびのび
自由でゆったりとした
こころの、からだの
環境の状態
のびのび のびのび
ぼくも相方を見つけて
人のこころを
ぐーんと広く
してみたいもんだな
(c) 2012 あわやまり